この記事は前回からのテーマ
「絶対矛盾的自己同一」の
続きです。
引き続き、例を挙げていきます。
絶対矛盾的自己同一
絶対矛盾的自己同一の例 ④ 「永遠と今」
永遠と今は別物のようにみえます。
「永遠」は過ぎ去らないし、
「今」は過ぎ去ります。
しかし、
「今」は、常に、深く、
「永遠」につながっています。
「永遠の命」をくれた祖母の話
私の祖母が亡くなったとき、
お寺で供養してもらいました。
そのときの住職の言葉が
今でも残っています。
「皆さんのお母さんは
祖先から宇宙へと連綿とつながる
“永遠の命” を皆さんに授けてくれた。」
当時の私は、このことが
理解出来ませんでした。
なぜなら、命は永遠ではなく、
限りがあるものだからです。
しかし、本書を読んでから
理解出来たことがあります。
人が永遠に生きてはいられないという考えは
生物的生命に基づいた考えです。
生物的に、祖母は亡くなりましたが、
私たちの心の中に宿り直しています。
そして、精神的支柱となっています。
死を乗り越えてなお、
存在し続ける何か。
死んでも他者の中で在り続ける何か。
西田は、これを、
「人格的生命」と
定義しました。
死を乗り越えてなお、
よき存在として生き続けるなら
それは 『善』 である。
と西田はいいたかったのだと
思います。
祖母が私たちの心に
良い影響を残し、
そして、私たちも
よくあろうとすれば
その命は永遠です。
それを住職は
伝えたかったのだと
思います。
次回も引き続き、
「絶対矛盾的自己同一」の
例を挙げていきたいと思います。
【本の要約・気づき】『善の研究』西田幾多郎 ――日本最初の哲学書 Part6
(次回リンク予定地)
【本の要約・気づき】『善の研究』西田幾多郎 ――日本最初の哲学書 Part4
https://amzn.to/3L8FiJO
哲学 関連記事:カント著『純粋理性批判』
哲学 関連記事:ハイデガー『存在と時間』
哲学 関連記事:マルクスガブリエル著 『なぜ世界は存在しないのか』
あ

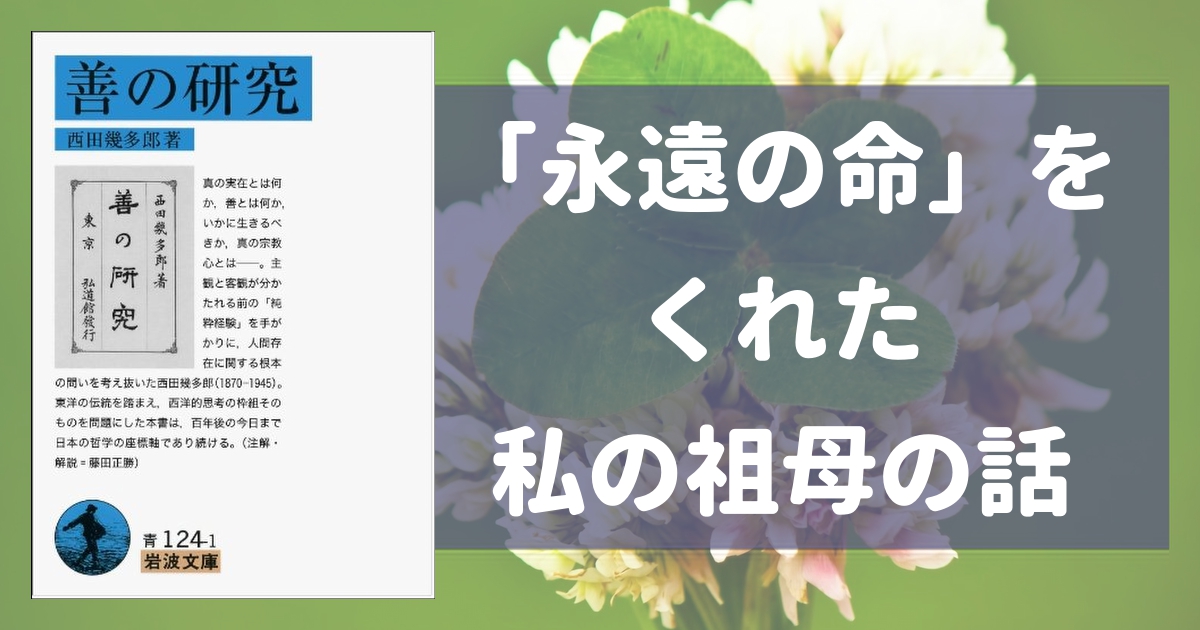
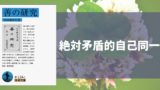



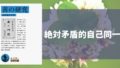
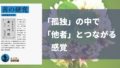
コメント